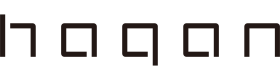記事: “家業” を “志業” へ── 日本酒業界に挑む山本典正の軌跡(前編)
“家業” を “志業” へ── 日本酒業界に挑む山本典正の軌跡(前編)
「酒蔵の息子」ではなく、「経営者としての自分」。
平和酒造(和歌山県)の代表取締役社長・山本典正さんのキャリアは、家業を継いだ4代目という枠にとどまらない。自らの意思で経営の道を選び、独自の哲学と手法で新しい価値を創り続けてきた。そんな山本さんに「ビジネスアスリート」としての軌跡と覚悟を伺った。

平和酒造株式会社 代表取締役社長の山本典正さん
経営者としての「原点」
「将来は実家の酒蔵を継いで欲しい」
山本さんは、幼少期から両親にそう言われて育ってきた。酒蔵の長男として生まれたからには、もちろん継ぐ覚悟はあった。その一方で、「東京で起業して経営者になりたい」という思いも消えずにいた。
小学校6年生の頃から、各界の著名人が連載する日経新聞のコラム『私の履歴書』を愛読。本人曰く「ちょっと変わった小学生だった」という。京都大学経済学部に在学中、革新的な技術やアイデアをもとに、新たな製品やサービスの開発、提供を目指すスタートアップ企業でインターンを経験。卒業後もそのまま同じ会社で働き、起業や経営に触れる日々を過ごす。当時、六本木ヒルズを拠点に活躍した “ヒルズ族” と呼ばれる若いIT起業家への憧れもあったが、なかなかチャンスをつかめずにいた。
そんな中、父から「蔵に戻ってきて欲しい」と声がかかった。仕事での成果も出始め、後ろ髪を引かれながらも、山本さんは実家へ戻る決意をした。25歳の時だった。

ただ、戻った理由が “日本酒への情熱” かと言えば、そうではなかった。 山本さんにとっての原点は、何よりも「経営者になりたい」という意思と、「美味しいものが好き」という感覚だったという。
「大学時代から、ちょっと背伸びをして高級店のランチを食べに行くのが楽しみでした」と山本さん。酒はあまり強くなかったが、社会人時代、深夜まで働いた後の一杯の日本酒のおいしさが心に刻まれた。そんな日々が、彼に「日本酒が傍らにある心豊かな生活」を体感させた。その結果、酒の世界に入る土壌が自然と育っていった。
若き4代目の葛藤と挑戦
戻った当初、山本さんを待っていたのは、同世代の蔵人との “壁” だった。
「父の時代の古い組織体制から働く彼らは、特に酒造りに情熱があったわけではありませんでした。就職難の時代で、他に就職先がなかったから、とりあえず入社した方も多かったように思います。そんな中、東京からやる気満々&意識高い系の息子が帰ってきたわけですから、蔵人としたらそれはもうやりにくいですよね。彼らにとったら、いけすかないキャラだったと思いますよ」
同世代でありながら、山本さんとの意識の差は歴然。だが山本さんは相手に媚びることなく、むしろ自分の意見をどんどん伝えていくようにした。そこには「酒蔵をより良くしていきたい」という熱い思いがあったからだ。
蔵に帰ってきた当時は特に役職もなかったので、自ら名刺に営業課長という肩書を入れた。上司となる部長はおろか、営業部すらない “ひとり営業部” の現場でひたすら汗をかいた。
初のヒット商品「鶴梅」が経営転換のきっかけに
山本さんに酒蔵の経営者としての自信が芽生えたのは、家業に戻って2年目のこと。山本さんが商品開発からデザインに至るまで主導したリキュール『鶴梅』シリーズの大ヒットがターニングポイントとなった。『鶴梅』は地元の梅を原材料にした日本酒ベースの梅酒。甘さ控え目で、梅の風味を最大限に生かした味が女性を中心に支持を得た。楽天市場のリキュール部門でも1位となり、瞬く間に蔵の看板商品に。営業をかけなくても、1日に10〜15件の問い合わせが入ってくるようになった。
山本さんは『鶴梅』の販売を機に、父の時代からの販路も変えた。一般流通から特約店契約と呼ばれる限定流通にしたのだ。特約店とはいわば「酒蔵のお墨付きをもらった管理の行き届いた店」。特約店と取引することで、『鶴梅』はもちろん、蔵全体のブランド価値を高めることにつながった。

平和酒造のヒット商品『鶴梅』
ブランド転換と人材の未来戦略
山本さんが導入した特約店制度は、単なる販売の枠を超えた「パートナーシップ型のブランド構築」。父の時代に主流だった「安い商品をたくさん売る」路線から、「高品質の商品を、付加価値を高めて売る」スタイルへと大きく転換した。
山本さんは価格競争ではなく “価値” で勝つ路線へ舵を切ったのだ。
「父の代では安価なパック酒を大量生産し、低価格で売るスタイル。でも僕は、それを続ける未来が見えませんでした」
伏見や灘にある大手メーカーに価格で追随するビジネスではなく、品質で勝負する新路線。『鶴梅』を起点に、蔵の看板ブランド『KID』をはじめとする高品質商品が続々と生まれた。日本酒「KID」の名前は、産地である紀州(Kishu)と、英語で「子供」を意味するKIDの二つの意味を込めたもの。これから日本酒文化を育てていきたいという思いを象徴しており、若者や海外の人にも親しみやすいように、『KID』と名付けた。

そして山本さんはさらに改革を行っていく。蔵人を新卒採用に切り替えたのだ。
「人はコストではなく投資であり財産。だからこそ、高粗利のビジネスモデルが
必要でした」
「他に就職先がないから」と来る人ではなく、「未来を共に創る仲間」として人を迎える時代へ。「酒で人を感動させる」には、それを本気で信じる人材が必要だった。だからこそ、仕組みと文化、両面からの改革を山本さんは同時に進めていった。父との意見の違いにも何度もぶつかりながら、「時間が解決する」と信じて対話を重ねて今年で20年。山本さんの経営は、単なる事業承継ではなく、“未来への覚悟” だった。
※後編に続く。
山本典正
1978 年生まれ。京都大学経済学部経営学科卒業。東京の人材系ベンチャー企業を経て、2004 年に平和酒造へ入社。人生に豊かな彩りを添えられるお酒を届けたいとの想いで、日本酒「紀土」、リキュール「鶴梅」を立ち上げ。2016年より、クラフトビール「平和クラフト」を発売。斜陽産業と言われる酒造業界において新風を吹かせるべく、若い醸造家の育成に注力。伝統と革新をもって酒造りを行う一方、日本酒の魅力を伝える活動を精力的に行っている。2019年4月、代表取締役社長就任