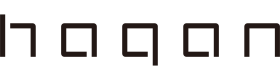“家業” を “志業” へ── 日本酒業界に挑む山本典正の軌跡(後編)
前編では、平和酒造の4代目として家業を継ぎ、改革に挑んできた山本典正さんの軌跡を追った。後編では都心での挑戦、経営者としての覚悟、そして未来へのビジョンを伺う。山本さんが語る「志業」としての酒造りとは何か──その本質に迫った。
都心にこそ、酒を醸す場を──「ブルワリーパブ」という挑戦
ここ数年、都心を筆頭に地方都市においてマイクロブルワリーが人気を呼んでいる。マイクロブルワリーとは、生産規模が限られた小規模の醸造所を指す。クラフト感あふれる酒を少量多品種で造るスタイルで、地域密着型の展開や、消費者との距離の近さも魅力だ。2022年、東京・兜町に誕生した『平和どぶろく兜町醸造所』もその1つ。店内で仕込んだどぶろくを、その場で味わえる稀有なブルワリーパブだ。

平和どぶろく兜町醸造所
「クラフトビールを主体にしたブルワリーパブは多々ありますが、米のお酒を出すところはほとんどない。そこに可能性を感じました」と山本さんは語る。
人が集う都心に店を構えることで、どぶろくはもちろん、日本酒と飲み手の距離を縮めたい。山本さんがそんな思いをもってスタートした『平和どぶろく醸造所』は、飲み手と蔵をつなぐ大事な”タッチポイント”なのだ。
ここで造られるどぶろくの種類は実に豊富。和歌山名産の山椒を使ったものや、イチゴの香り漂うフルーツ系など、ただ飲むだけでなく、楽しむ&味わう酒として、若者や海外の観光客など幅広いファンをも取り込んでいる。また、どぶろく以外にも『紀土』やクラフトビール『平和クラフト』も飲めるのが嬉しい。
さらに2025 年春には、大阪・なんばにも同様の店舗をオープン。東京・兜町、そして大阪・なんばという都市型の立地でどぶろくを仕込んで飲ませるという発想が、日本酒文化にも新風を吹き込んでいる。このような新しい発想を具現化できたのには、山本さんが築いてきた人との“縁”も影響している。

平和どぶろく難波醸造所
人との縁は、プロダクトで繋がる──“認められる”ための本質とは
堀江貴文氏や中田英寿氏など、名だたる著名人とも親交のある山本さんだが、「すべてはプロダクトありき」と言い切る。
「堀江さん、中田さんにしても、日本酒が大好きなんですね。お二人とも僕というより、うちのお酒が好きで、評価していただいているんだと思います」
そんな風に謙遜するところも、山本さんらしい。
堀江氏や中田氏をはじめ、山本さんとつきあいのある著名人が、まず評価するのは酒の味。山本さん自身、家業に就いてから、その一点に全精力を注いできた。今もなお、日々30~50 種類の利き酒を行い、社員ともども味覚のトレーニングに余念がない。
蔵元として、経営者として、自らの手で価値を生み出す。その愚直なまでの姿勢が、良縁を呼び込み、信頼を得る源泉となっている。こうした努力の継続には、何よりも体力と持続力が必要だ。だからこそ山本さんは、日々のコンディション管理に徹底している。
経営者に休みはない──365日稼働を可能にする“身体”と“ツール”
山本さんにとって、コンディション管理はビジネスの基盤。とは言え、彼に「休日」の概念はない。それを支えているのは‘‘鍛え抜かれた身体”だ。
「週4~5日は走っています。10キロは走りますね。冬はスキー、時々ゴルフもしています」

こうした有酸素運動以外にも、筋トレやストレッチ、睡眠管理、サプリメントでの栄養補給も欠かさない。──健康が整えば、判断は冴え、運も味方につく。だからこそ、体調を整えることを「経営戦略の一つ」として山本さんは捉えている。その戦略の中核にあるのが、スマートフォンという‘‘現代の武器”だ。
スマホは“刀”であり“相棒”──HAGANに託す「感覚の延長」
山本さんにとって、スマートフォンは、ビジネスで戦うための武器のようなもの。
「なくしたら青ざめます。スケジュールも、移動も、全てが止まる」と苦笑する。そんな大事なビジネスツールだからこそ、スマホケースにもこだわりがある。
今回、山本さんが手にしたのはHAGAN のケース。手に持ったときの感触、スーツ姿にも映える質感、そして自分らしさを表現するカラ—―すべてに満足しているという。

「グリーンを選んだのは、気分を変えたかったから。しっくりきたんですよね」
ビジネスにおけるグリーンは、成長、再生、誠実を象徴する色とも言われる。挫折を経て、時間をかけて人と組織を育て、今の平和酒造を築き上げた山本さん。その歩みに寄り添うように、グリーンのHAGAN ケースは、偶然のようでいて必然だったのかもしれない。
HAGAN のケースは、単なる保護具ではない。山本さんにとって、日々の決断を共にする“相棒”であり、経営者としての哲学を映す延長線にある存在と言ってもいい。
こうしたツールヘのこだわりは、山本さんの経営スタイルの核心を物語っている。そして、それは過去、そして未来へともリンクしているのだ。
10年の苦悩と今──“万人に愛される”より、自分の覚悟を貫く
成功の陰には、必ず痛みがある。創業当初の10 年間、山本さんは多くの人達と向き合ってきた。陰口もあった。だが、そのすべてを「未熟だった自分への学びだった」と受け止めている。
「僕は万人に愛されるタイプではない。でも、それでもいい。経営とは、自分の“我”を押し通すことと、抑えることのバランスなんです」
今では社員の定着率も上がり、ブランドカもついてきた。時間をかけ、理念を浸透させ、経営を‘‘志業”へと昇華させてきた山本さん。こうして築き上げた平和酒造を、彼は次なるステージヘと導こうとしている。

道なき道を行け──世界に挑む、その背中が次代を導く
現在、月に2 回は海外出張。時には西海岸へ“一泊のみ”で往復する弾丸スケジュールをこなす。だが山本さんは疲れを見せない。
「これからの日本酒は、世界に打って出なきゃいけない。最初に扉を開ける存在でいたいですね」
既存のスタイルをなぞるのではなく、常に自分たちの新しいやり方で道を切り開く。それが山本さんの信条だ。
最後に「座右の銘は?」と尋ねると、彼は静かに言った。
「僕の前に道はない、僕の後ろに道はできる──高村光太郎の詩ですね。そうありたいと思って、ここまで来ました」
そう話す山本さんの手にはスマートフォン、そしてそれを包み込むHAGAN のケース。そのひとつひとつが、「山本典正」というビジネスアスリートの衿持を映し出していた。
山本典正
1978 年生まれ。京都大学経済学部経営学科卒業。東京の人材系ベンチャー企業を経て、2004 年に平和酒造へ入社。人生に豊かな彩りを添えられるお酒を届けたいとの想いで、日本酒「紀土」、リキュール「鶴梅」を立ち上げ。2016年より、クラフトビール「平和クラフト」を発売。斜陽産業と言われる酒造業界において新風を吹かせるべく、若い醸造家の育成に注力。伝統と革新をもって酒造りを行う一方、日本酒の魅力を伝える活動を精力的に行っている。2019年4月、代表取締役社長就任