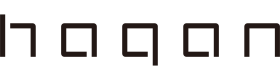記事: 【NEW】老舗を引き受ける覚悟──引き受ける経営(後編)
【NEW】老舗を引き受ける覚悟──引き受ける経営(後編)
赤字を止めるという外科手術を終えた後、木村光伯氏の前に残ったのは、安堵ではなく「自身への問い」だった。この会社は、何のために存在しているのか。誰を笑顔にしたいのか。数字を立て直すことと、価値を生み出すことは、別の仕事だ。守る経営から、その先へ。木村氏の足跡を追う。

マニュアル化が品質を壊した瞬間
赤字脱却後、更なる合理化と効率化を目指し、木村屋総本店では経営コンサルタントを入れた改革が進められた。
誰でも同じ品質のパンを作れるようにする。
職人に依存しない体制をつくる。
そのために導入したのが、徹底したマニュアル化と多能工化だった。ミキサー担当者は、決められた分量の粉を入れ、決まった分数だけミキサーを回す。材料を入れるタイミングも、回転時間も、すべて数値で管理される。
一見すると、合理的な仕組みだった。だが、現実は違った。酵母という微生物を使って作るパンは生き物。その日の気温や湿度、発酵の進み具合によって、同じ条件でも、生地の状態は変わる。結果として、品質は安定しなかった。それどころか、食パンが真ん中からポキッと折れたり、焼き上がりも日によってばらついたりすることがあった。現場に理由を尋ねると、返ってきたのはこうした答えだった。
「マニュアル通りにやっています」
この答えを聞いて、木村氏は愕然とした。
マニュアルでは、価値は生まれない
かつての職人たちは、数値ではなく感覚で判断していた。
「今日は空気が乾いているから水分を少し足そう」
「肌がピリつくから焼成温度を上げよう」
それは勘や気分ではなく、長年の経験によって培われた技術だった。マニュアル化によって失われたのは作業の自由ではなく、判断する力だった。
この気づきを確信へと変えたのが、銘酒『獺祭』を造る旭酒造の現場だった。木村氏は当初、大規模化した蔵を見て、フルオートメーションで効率的に酒を造っているのだろうと想像していたという。だが実際に目にしたのは、七十本以上の小さなタンクを前に、人の手で一つひとつ状態を確かめる姿だった。
「データはちゃんと取っている。でも、最後は人が触らないとわからないと桜井博士会長から言われたんです。米の塊がどこにあるかなんて、自動化したら見えないでしょうと」
温度や発酵の状態はデータで可視化されている。それでも、酒造りにおける最後の判断は人の手に委ねられていた。その光景を前に、木村氏は腑に落ちたという。
「合理化だけではダメなんだなと。人の思いとか、向き合い方をどう残していくか。その土台づくりを一緒にやらないと、いいものは作れないんだと思いました」
その気づきが、職人たちの言葉や感覚を拾い上げ、理念として言語化していく作業へとつながっていった。

理念は、どこから来たのか?祖先と「思い」を継ぐという感覚
現場で交わされてきた言葉や感覚を手がかりに、理念の輪郭を探っていく中、木村氏が向き合ったのは、「その言葉の根はどこにあるのか」という問いだった。そう考えたとき、木村氏の思考は自然と、自身が育ってきた時間へとさかのぼっていった。それは祖先との向き合い方である。
木村家の菩提寺には、墓石が二つ並んでいる。一つは初代・木村安兵衛をはじめとする遺骨が眠る墓。もう一つは「奥津城と呼ばれる墓石で、その下に骨はない。そこに眠っているのは、先人たちの「思い」だと、父から教えられてきた。
「お墓を洗い、手を合わせる度に、この会社は自分のものではなく、先に生きた人たちから預かったものなのだと実感します。経営判断に迷った時も、初代ならどう考えるだろうか、祖父ならどんな決断を下すだろうかと、自らに問いかけています。
過去を神格化するわけではない。
だが、切り離すこともしない。
先人たちは何を大切にし、どんな思いでパンを作ってきたのか。
その問いに向き合い、現場の声と重ね合わせながら言葉を探っていく中で、木村氏がたどり着いたのが、「食で感動を繋ぎ、幸福(しあわせ)の輪を広げる」という経営理念だった。
この理念は、掲げるための言葉ではなく、判断に迷った時に立ち返る基準として機能している。社員の評価や行動目標とも結びつき、組織の共通言語として使われている。
革新は理念の延長線上にある
木村屋總本店の歴史を振り返ると、革新はいつも、理念から外れない場所で生まれてきたことがわかる。明治初期、西洋から伝わったパンは、日本人の嗜好には受け入れられなかったからだ。そこで初代が着目したのが、日本人に親しまれていた酒まんじゅうだった。西洋の製パン技術に、和の発想を掛け合わせる。
そうして生まれたのが、「酒種あんぱん」である。
「新しいものが入ってきたときに、それをそのまま出すのではなく、一度ちゃんと受け止めて、日本人の感覚に合う形に噛み砕いていったんだと思うんです。初代たちは、売れるかどうか以前に、どうすれば喜んでもらえる華を考えていたんじゃないでしょうか」
新しいものを無条件に取り入れるのではない。だが、拒むものでもない。自分たちの文化や感覚と融合させ、新しい価値として差し出す。その姿勢は、創業当時から今も変わっていない。


「新しさそのものを追いかけると、どうしてもブレてしまう。そうではなくて、それが本当に感動につながるのか、幸福の輪を広げるのか。そこから外れていないかを、いつも自分に問い直しています」
革新は理念を拠り所にしながら、時代に合わせて更新し続けること。木村屋總本店の看板商品・酒種あんぱんの誕生は、その最初の実例だった。
理念は社会へと開かれていく。「ぱん食い競走」と繋がりの輪
理念の射程は、組織の内側だけにとどまらない。木村氏が副会長を務めるいっ“ぱん”社団法人ぱん食い競走協会が主催するぱん食い競走にも、彼の思想、理念が息づいている。ぱん食い競走は、年齢や性別、障がいの有無を問わず、誰もが参加できる競技で、食を通じて人が集い、笑顔が生まれるスポーツだ。勝ち負け以上に、同じ場で走り、笑い、あんぱんを頬張る時間そのものに価値がある。それ自体が、「食で感動を繋ぎ、幸福の輪を広げる」という理念の実践でもある。
さらに、競技として終わるだけではない。大会後には、参加者の人数分のパンを地元の子ども食堂に寄付する活動も行われ、地域のつながりと支え合いを生む社会貢献につながっている。
理念は「掲げたら終わり」ではない。行動に移され、社会に開かれていくことで、はじめて力を持つ。木村氏のこの感覚は、彼が選ぶ「道具」にも通じていく。

道具にも思想は宿る。「HAGAN」という選択
理念を行動に落とし込み、社会へひらいていく。木村光伯氏にとって、その姿勢は特別な場面だけで発揮されるものではない。スマートフォンをはじめとする日常に使う「道具の選択」にも、同じ判断軸が貫かれている。
木村氏にとってスマートフォンは、単なる連絡手段ではない。人と人をつなぎ、判断を下し、仕事と向き合うための「現場」そのものだ。その現場を包む道具として、『HAGAN』のスマホケースを手にした時、木村氏がまず言及したのはその「質感」だった。
「上質なスーツを思わせるケースだなと思いました。クロコダイルの革の質感はもちろん、ケースの細部に職人の技が見て取れますね」


きちんと作られたものを手にすることで、自分自身の向き合い方も整う。木村氏の言葉からは、そんな実感がにじむ。
特に印象的だったのは、「細部」への視線だ。そこに価値を見出す姿勢は、パン作りや経営において、木村氏自身が積み重ねてきた判断とも重なっている。
選んだカラーはブリティッシュグリーン。黒や茶が選ばれやすい中で、あえて差し色となる色だ。ブリティッシュグリーンに象徴される控えめで意思のある佇まいが、木村氏の在り方そのものを映しているようだった。
木村光伯
1978年生まれ、東京都出身 学習院大学経済学部卒
グロービス経営大学院経営学修士(MBA)
一般社団法人ぱん食い競走大会(設立準備中)副会長
レゴ®シリアスプレイ®トレーニング修了 認定LPSファシリテーター
2001年大学卒業後、家業である木村屋總本店に入社し、翌年米国カンザス州にある American Institute of Baking(AIB)に留学し、製パン技術ならびに安全衛生管理を取得。
帰国後2006年より現職。おいしいスポーツで世界が広がる。2024年より、ぱん食い競走協会副会長として、 スポーツぱんシップに則り、楽しいぱん食い競走文化を広め、幸福を世界に広げ、 ぱんを通じて世界と繋がり、世界平和を実現するというミッションのもと実施している。